
日本の百科事典
 Sport
Sport


柔道(じゅうどう)は、「柔」(やわら)の術を用いての徳性涵養(とくせいかんよう)を目的とした芸道、武道のことである。20世紀終盤までに、その修養に用いられる嘉納治五郎流・講道館流の柔術技法を元にした理念を指して「柔道」と呼ぶことが一般化している。柔道は、投技・固技・当身技の三つを主体とする武術・武道、そしてそれを元にした社会教育的な大系となっている。
古武道の柔術から発展した武道で、投技、固技、当身技を主体とした技法を持つ。明治時代に警察や学校に普及し、第二次大戦後には国際競技連盟の国際柔道連盟の設立や乱取り試合がオリンピック競技に採用されるなど広く世界的な普及に成功している。
スポーツ競技・格闘技でもあるが、講道館柔道においては「精力善用」「自他共栄」を基本理念とし、競技における単なる勝利至上主義ではなく、身体・精神の鍛錬と教育を目的としている[注釈 1]。

相撲(すもう)は、土俵の上で力士が組合って戦う形を取る日本古来の神事や祭で、同時にそれを起源とする武芸や武道の一つ。興行としては大相撲が行われている。日本由来の武道・格闘技・スポーツとして国際的にも認知されている。
相撲は古代以前(伝承としては神話の時代)に始まったとされ、江戸時代には庶民の娯楽として隆盛を極めた[2]。
現代の相撲について民俗学の研究ではその担い手と歴史的系譜から、相撲を生業とする人々による興行相撲から連なる大相撲、学生相撲や実業団相撲などのアマチュア相撲、地方の神事や余興として行われてきた相撲(新田一郎や池田雅雄らによって「素人相撲」に分類された草相撲、野相撲、奉納相撲など)の3つに区分する[3]。特に日本相撲協会が主催するスポーツの興行としての大相撲が有名だが、神事に由来するため、他のプロスポーツと比べて礼儀作法などが重視されており、生活様式や風貌なども旧来の風俗が比較的維持されるなど文化的な側面もある。
日本国内外で同じような形態の格闘技としては、沖縄本島の沖縄角力(シマ)、モンゴルのブフ、中国のシュアイジャオ、朝鮮半島のシルム、トルコのヤールギュレシ、セネガルのランブなどがある。それぞれ独自の名前を持つが、日本国内で紹介される場合には何々相撲(沖縄相撲(琉角力)、モンゴル相撲、トルコ相撲など)、といった名で呼ばれることが多い。

 History
History
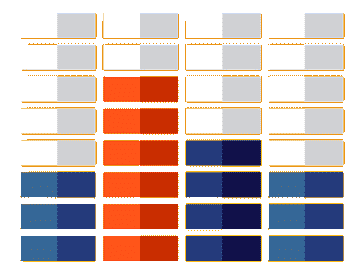 Music charts
Music charts